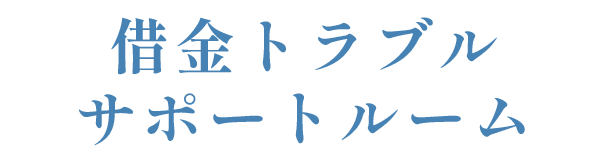財産隠しがバレると、免責不許可事由として自己破産が認められないほか、刑事事件に問われる可能性もあります。
それぞれのリスクについて詳しく解説します。
①免責不許可事由
免責不許可事由とは、裁判所から自己破産が認められないことを指します。
自己破産によって返済義務を免除されるかどうかの最終的な判断は裁判所が行いますが、財産隠しが発覚すると借金の免責が認められません。
免責不許可事由に該当する内容について、破産法では以下のようにも記載されています。
”債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。”(引用:e-GOV法令検索「
破産法 第252条」)
自己破産が認められないと、当然ながら借金の返済義務もなくなりません。
また、不許可になった場合は1週間以内に裁判所に「即時抗告」という異議申し立てができますが、財産隠しの場合は決定が覆らない可能性が非常に高いです。
②刑事事件
財産隠しをした場合「詐欺破産罪」が成立する場合があります。
詐欺破産罪については、破産法について以下のように定められています。
”破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第4号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
1 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
2 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
3 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
4 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為”(引用:e-GOV法令検索「
破産法 第265条」)
このように、財産隠しをするために偽ったり、改変したり、処分するなどの債権者の利益を害する対応を意図的に行った場合、詐欺破産罪として10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が課せられることになります。
また、財産隠しのために友人や家族に協力を得た場合、協力者についても詐欺破産罪に問われる可能性があります。