自己破産について、このような悩みや疑問はありませんか?
「メリットとデメリットを知りたい」
「自己破産にデメリットがないってホント?」
自己破産に”借金がチャラになる”というイメージを持っている方も多く、インターネットでは”メリットしかない”や”デメリットがない”と言われることも多いです。
しかし、自己破産にはデメリットも存在するため、メリットとデメリットを両方理解したうえで手続きを行うことが非常に大切になります。
本記事では、自己破産のメリットとデメリットについて徹底解説します。
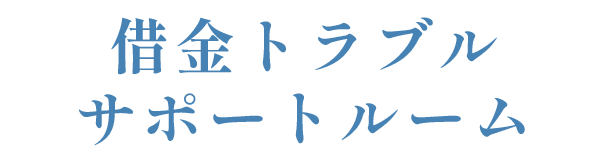
CONTENTS コンテンツ
自己破産
2025.04.01
自己破産について、このような悩みや疑問はありませんか?
「メリットとデメリットを知りたい」
「自己破産にデメリットがないってホント?」
自己破産に”借金がチャラになる”というイメージを持っている方も多く、インターネットでは”メリットしかない”や”デメリットがない”と言われることも多いです。
しかし、自己破産にはデメリットも存在するため、メリットとデメリットを両方理解したうえで手続きを行うことが非常に大切になります。
本記事では、自己破産のメリットとデメリットについて徹底解説します。
自己破産にメリットとデメリットがあるのは知っていても、そもそもの仕組みや手続の流れを理解していない方も多いでしょう。
自己破産とは?仕組みや同時廃止と管財事件の違い、手続きの流れを解説
の記事では、破産手続きの種類や流れを詳しく説明していますので、まずはこちらをご覧ください。
一定の価値のある財産、たとえば車は原則として処分対象になります。
ただし状況によっては残せる可能性もあります。詳しくは
自己破産すると車はどうなる?|残せるケース・失うケース・対応策を司法書士が解説
をご覧ください。
「どうしても車を残したい」という方へ。
実際にどんなケースなら手元に残せるのかを解説した記事があります。ぜひ参考にしてください。
→ 自己破産すると車はどうなる?|残せるケース・失うケース・対応策を司法書士が解説
自己破産のご相談は司法書士法人エベレストへ
借金問題は早めの相談が解決への近道です。
司法書士法人エベレストが生活再建への第一歩をサポートします。