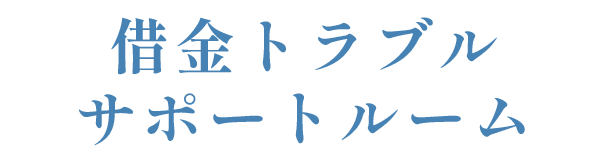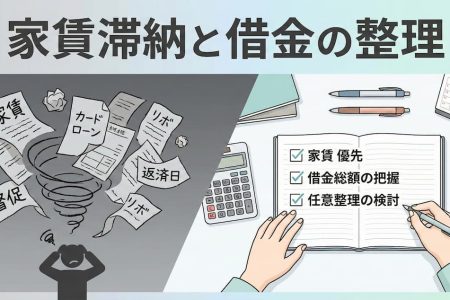借金やカードの返済が遅れると、「遅延損害金」というお金がかかります。名前だけ聞くと難しそうに感じますが、実際には「遅れた日数に応じて上乗せされる利息」と考えると分かりやすいでしょう。
問題は、この遅延損害金が通常の利息より高く設定されているため、放置するとあっという間に増えてしまうことです。
さらに長期間遅れると、信用情報に記録が残ったり、裁判や差押えにつながることもあります。こうした不安を少しでも減らすには、まず「どれくらい増えるのか」を知り、支払えないときの解決策を理解しておくことが大切です。
本記事では、計算方法や放置した場合のリスク、そして支払えないときに取れる選択肢を、司法書士の視点から分かりやすく解説します。
目次
遅延損害金とは?発生する理由と特徴
支払いが遅れたときに請求されるのが「遅延損害金」です。法律用語のようで分かりにくく感じるかもしれませんが、実際には「遅れた日数に応じて上乗せされる利息」と考えるとイメージしやすいでしょう。
「いくら増えるのか」「どこまで請求されるのか」という不安を解消するには、まずこの遅延損害金の正体を正しく押さえることが近道です。
遅延損害金は、通常の利息よりも高い利率で設定されており、返済が遅れるほど負担が大きくなります。たとえば通常の利息が年15%程度であっても、遅延損害金は18〜20%に上がるのが一般的です。これは「期日を守らなかった分、追加の負担をしてください」という契約上のルールだからです。
計算は日割りで行われ、延滞した翌日から増え続けます。数日なら数百円で済んでも、放置すると雪だるま式に膨らみ、やがて元金より大きな金額になるケースもあります。
大切なのは、「聞き慣れない言葉だから難しそう」と感じても、一度は契約書やカード規約の「遅延損害金」の欄を確認してみることです。利率と起算日を把握するだけで、今の状況と将来の負担が見えやすくなり、安心につながります。
遅延損害金の利率はどのように設定されているか?
遅延損害金の利率には、法定利率と約定利率の2種類があります。民法では、法定利率は3%とされていますが、当事者間で別の利率を決めることができ、これを約定利率と呼びます。以前は5%で固定されていましたが、民法の改正により、当初3%に設定し、その後3年ごとに見直す変動制に変わりました。
約定利率が法定利率を超える場合、約定利率が適用されますが、上限が存在します。例えば、クレジットカードのショッピング利用には消費者契約法によって上限が14.6%と定められています。
また、お金の貸し借りには利息制限法が適用され、この法律により遅延損害金の上限は、利息制限法で定められた利率の1.46倍までとされています。遅延損害金の利率は元金の額によって異なり、具体的には以下の通りです(この上限を超える遅延損害金は無効)。
- 元本の額が10万円未満の場合 … 年29.2%
- 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 … 年26.28%
- 元本の額が100万円以上の場合 … 年21.9%
なお、消費者金融業者などの業者が貸付を行う際には、上限が20%に制限されています(利息制限法7条1項)。利息制限法は、借主が過剰な利息負担に苦しまないよう保護するための法律で、個人間の貸し借りにも適用されます。
遅延損害金の計算方法【具体例つき】
「いくら請求されるのか分からないまま」では対処のしようがありません。遅延損害金の計算方法を知ることで、延滞による追加負担の大きさを具体的に把握でき、早めの対応や相談につなげることができます。
計算式:延滞している元金 × 遅延損害金利率 × 延滞日数 ÷ 365日
ここでの利率は、契約に定められた「遅延損害金年率」をそのまま用います。多くのカードローンや消費者金融では18〜20%前後、クレジットカードのショッピング枠では14.6%が上限です。計算に用いる日数は返済期日の翌日から支払い完了日までの日数です。
一括返済を延滞した場合
100万円 × 18% × 30日 ÷ 365日 ≒ 14,794円
これは元金の約1.5%に相当します。1日あたりに換算すると約493円(年18% ÷ 365日)です。
1か月遅れるだけで元金の1.5%程度が加算されることになり、2か月遅れればその2倍、3か月なら約4万4,000円まで膨れ上がります。
特に支払いの遅延が続き「期限の利益」を失うと、借入残高全額が延滞元金とみなされ、同じ計算式で遅延損害金が発生します。その場合、負担は一気に跳ね上がるため注意が必要です。
分割返済を延滞した場合
分割払いの場合は「その回の元金部分」に対して遅延損害金が発生します。
たとえば、月々3万円を返済している契約で遅延損害金利率が年20%のところ、1回の支払いを20日遅らせたとします。
3万円 × 20% × 20日 ÷ 365日 ≒ 329円
1回の遅れでは数百円に過ぎませんが、この延滞を何度も繰り返したり、複数回分を滞納し続けると状況は変わります。2回分・3回分と滞納が重なれば、その都度計算される遅延損害金が累積し、返済額全体に対する遅延損害金まで請求されることもあります。
さらに、滞納が2〜3か月続くと期限の利益を失い、残高全額を対象に遅延損害金がかかるケースも多いのです。
計算で押さえておきたいポイント
- 年率を日率に換算する:利率(%)を365で割ると1日あたりの遅延損害金率が求められます(例:年18% → 1日あたり約0.049%)。
- 延滞日数は翌日から:返済期日翌日から支払い完了日までの日数を掛けます。週末や祝日でも発生します。
- 元金部分のみ対象:分割返済では、その期に支払うべき元金部分に対してのみ発生。ただし期限の利益を失うと残高全額に適用。
遅延損害金は法令に基づく正当な請求であり、放置すれば日々増え続けます。まずは契約書やカード規約に記載されている遅延損害金の年率と起算日を確認し、自分がどの程度の負担になるか試算してみましょう。
払えないときの3つの解決策
まずは今できることを確認してみませんか?
返済の猶予や条件変更など、考えられる選択肢はいくつもあります。
「自分にはどれが合うのか」を整理するだけでも気持ちが楽になります。
LINEなら24時間受付。匿名でのご相談も可能です。
返済が遅れ、「もう払えないかもしれない…」と感じると、怖くて何もしたくなくなるものです。
でも何もしないままでは、遅延損害金が増え続け、差押えなどの大きなリスクにつながります。この章では、そんな不安を抱えた人が知っておくべき3つの対処法を分かりやすく紹介します。
解決策1 まずは支払いの相談をする
返済が間に合わないと分かった時点で、そのまま放置せず、必ず借入先に連絡することが大切です。
期日前に「支払えない理由」と「支払える予定日」を伝えておけば、同じ内容の催促電話が繰り返しかかってくる可能性は低くなります。実際、こちらから誠実に電話へ応じるだけで「返済意思がある」と受け取られ、貸主も柔軟な対応を検討しやすくなります。
ただし注意点として、返済条件の変更や猶予に応じてもらえるかどうかは債権者によって異なるため、必ずしも希望通りになるわけではありません。
また、すでに弁護士や司法書士に依頼している場合は、専門家を通じて交渉する方が安全かつ確実です。状況を正確に伝えられるだけでなく、貸主側も法的な解決手段を視野に入れやすくなるため、無理な取り立てを避けられるケースもあります。
解決方法2 返済条件を交渉して生活を立て直す
遅延損害金は基本的に発生しますが、交渉の場ではこれ以上負担を増やさないための条件変更が検討されることがあります。たとえば、
- 今後の利息をつけず、元金の返済に専念できるようにする
- 毎月の返済額や分割回数を調整し、無理のない返済計画にする
このような交渉は「任意整理」という手続きで行われます。司法書士や弁護士が債権者と直接やり取りし、返済を続けやすい現実的な計画をまとめます。裁判所を通さないため手続きが比較的シンプルで、財産を処分する必要もありません。
ただし、交渉に応じるかどうかや条件の内容は債権者によって異なります。専門家に依頼することで、各金融機関の対応傾向に合わせた提案ができ、合意に至る可能性を高められます。
解決方法3 裁判所を通じた法的手続きを検討する
任意整理での交渉でも返済の目途が立たない場合、裁判所を通じた法的な手続きを検討する段階に入ります。代表的なのが個人再生と自己破産です。
個人再生:
裁判所に申し立てることで借金を大幅に減額し、原則3年(事情により5年まで延長可)で分割返済していく制度です。借金総額や資産に応じた最低返済額が定められ、条件次第では元の借金を2割、場合によっては1割程度まで圧縮できることもあります。また、住宅ローンを従来通り返済することでマイホームを手放さずに済む「住宅資金特別条項」も利用可能です。「家を守りたい」「自己破産は避けたい」という方に有効な選択肢です。
自己破産:
裁判所に申し立てることで借金の返済義務そのものから解放される制度です。
生活に必要な最低限の財産は手元に残せますが、それ以上の資産は処分される場合があります。
また、財産が少ない場合は「同時廃止」で比較的短期間に終わりますが、一定の財産や免責に問題がある場合は「管財事件」となり、費用や期間が増えることもあります。
「返済が限界」「生活を立て直したい」という方にとって、最後の切り札となる解決方法です。
いずれの制度も心理的なハードルは大きいですが、早めに専門家へ相談することで最適な選択肢を見極められ、生活再建の道が開けます。
遅延損害金を放置するリスク
借金の返済を放置すると、まず遅延損害金が日ごとに膨らみ、返済負担はどんどん重くなっていきます。
さらに滞納が続くと、信用情報に延滞の記録が掲載される(いわゆるブラックリスト状態)ことになります。この状態になると、今後のローン契約やクレジットカードの新規発行・利用に大きな制限がかかります。
また、滞納期間が2〜3か月に及ぶと、一括請求を受ける可能性が高まります。督促を無視し続ければ、債権者が裁判を起こすリスクがさらに高まり、訴訟に発展するケースも少なくありません。
そして裁判所から書類が届いたにもかかわらず放置した場合、相手の主張通りの判決が出される危険性があります。その結果、債権者は債権回収のために、預貯金や給与、不動産などを差し押さえることが可能になります。
返済遅延を「少しのこと」と軽く考えるのは危険です。早めに司法書士などの専門家に相談することで、差押えなどの深刻な事態を避けられる可能性が高まります。
注意点とデメリットも理解しておこう
遅延損害金や債務整理に関しては、「手続きすればすぐに解決できる」と思われがちですが、いくつかの注意点やデメリットも理解しておく必要があります。
- 元金は基本的に残る:任意整理をしても、将来利息のカットや返済条件の調整が中心であり、借入の元金そのものが消えるわけではありません。
- 信用情報への影響:債務整理を行った場合は、一定期間、信用情報に記録されます。新たなローンやクレジットカードの利用は難しくなります。
- 費用と時間がかかる:個人再生や自己破産など裁判所を通じた手続きは、半年〜1年程度の期間がかかることがあり、専門家への費用負担も生じます。
- 資産を手放すリスク:自己破産では、住宅や車など一定の資産を処分しなければならない場合があります。生活に必要な範囲は残されますが、大きな決断が必要になります。
これらのデメリットは確かにありますが、裏を返せば「手続きを知らないまま放置する方が、はるかに大きな損失につながる」ということでもあります。正しい知識をもったうえで判断し、納得できる解決策を選ぶことが大切です。
遅延損害金が膨らんでいるのに減額提案?そのとき疑うべきこと
遅延損害金は本来であれば支払わなければならず、延滞が続けば続くほど膨らんでいくのが通常です。にもかかわらず、貸金業者から「遅延損害金を大幅に減額する」といった提案が出てきた場合は、かえって注意が必要です。
こうしたケースの背景には、借金が長期間支払われておらず、すでに時効が成立している可能性があります。たとえば、最後の返済から5年以上が経過していれば、時効援用によって遅延損害金を含めた返済義務そのものが消滅する場合もあります。
ところが、業者からの提案に安易に応じてしまうと、かえって時効の主張ができなくなるなど、不利な状況に陥ることがあります。
このような場面では、司法書士や弁護士などの専門家に相談し、時効の可能性を含めて正しく判断してもらうことが大切です。
まとめ
遅延損害金は、返済が遅れた場合に発生する一種のペナルティで、通常の利息より高い利率で計算されます。借金を放置すればするほど、遅延損害金が膨らんでいきます。
遅延損害金が膨らむと、返済の負担が大きくなっていきますし、長期間の滞納は、債権者からの裁判提起のリスクを高め、最終的には財産差し押さえの可能性もあります。
遅延損害金が膨らみ、支払いが難しくなった場合、自分で解決が難しいと感じたら、専門家(司法書士や弁護士)に相談することをお勧めします。